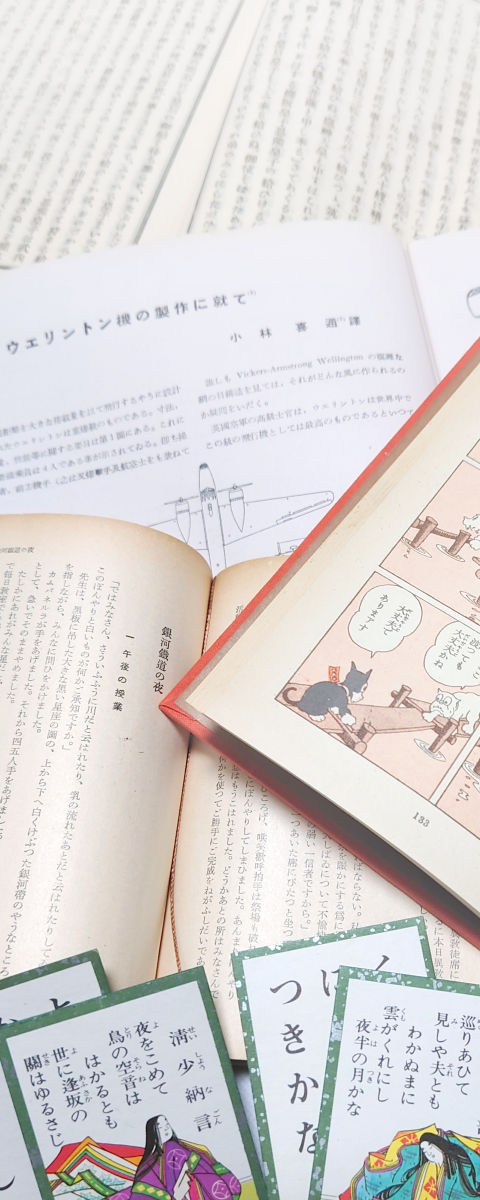
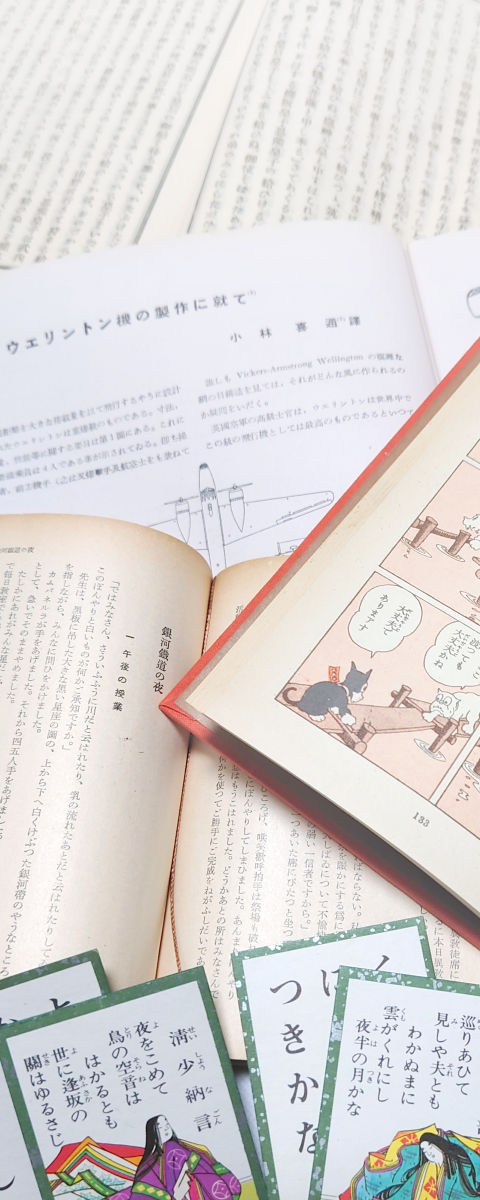
この文書では、義務教育で習ったはずの〝歴史的仮名遣い(旧かなづかい)〟を忘れてしまった方、または「とりあへず読めればよい」といふ方に向けて、その読み方を説明します。〝歴史的仮名遣い〟で書かれた文章を滞りなく読めるやうになる一助になれば幸ひです。
以降この文書では〝歴史的仮名遣い〟や〝旧かなづかい〟を、「本来のかなづかひ」といふ意味で一括して「正かなづかひ」と表記してゐます。
この文書は全般的に正かなづかひ〔捨て仮名あり〕で書いてゐます。ただし参考のために、文中で初出の単語には振り仮名として、また例示では丸括弧の中で、〝現代仮名遣い〟(一九八六年内閣告示)に基づく記載をしてゐます。
かなづかひとは、同音の仮名の書き分け方です。例へば、人々の繋がりを表す「きづな」は、〝現代仮名遣い〟の本則では「きずな」と書きますが、正かなづかひでは「つな (綱)・つなぐ」の意味に基づいて「きづな」と書きます。「づ」も「ず」も現代では同じ発音ですが、正かなづかひでは古来からの語の意味に基づいて仮名が使ひ分けられてゐます。
逆にいへば、かなづかひが違っても読み上げ方(発音)は同じです。例へば「思ひ出」を現代では普通「オモイデ」と読みます。「思ひ出」と書かれてゐるからといって「オモヒデ」と読む必要はありません。普段「今は春」を「イマワハル」と読むのと同じことです。
| ア段 | イ段 | ウ段 | エ段 | オ段 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ア行 | あ | い | う | え | お |
| カ行 | か | き | く | け | こ |
| サ行 | さ | し | す | せ | そ |
| タ行 | た | ち | つ | て | と |
| ナ行 | な | に | ぬ | ね | の |
| ハ行 | は | ひ | ふ | へ | ほ |
| マ行 | ま | み | む | め | も |
| ヤ行 | や | い | ゆ | え | よ |
| ラ行 | ら | り | る | れ | ろ |
| ワ行 | わ | ゐ | う | ゑ | を |
正かなづかひの読み方を知るには、まづ五十音図の行・段を把握しておくことが必要です。そこで本来の五十音図を覚えて下さい。「本来の」と勿体ぶったのは、現在の教育で用ゐられる「あいうえお表」とは違ふ部分があるためです。なほ「ん」はどの行・段にも属しないといふ考へ方により表からは除いてゐます。
ヤ行に「い・え」、ワ行に「う」がありますが、これらの読み方は文字通りア行の「い・う・え」と同じです。
ワ行の「ゐ」と「ゑ」については次の章で説明します。
正かなづかひではワ行の「ゐ・ゑ・を」がよく使はれます。
まづ「ゐ・ゑ」ですが、「ゐ」は「イ」、「ゑ」は「エ」と読みます。五十音図を見て「ゐ」がイ段、「ゑ」がエ段にあるのを確かめて下さい。なほ「ゐ」のカタカナは「ヰ」、「ゑ」は「ヱ」です。
「ゐ・ゑ」は仮名の元になった漢字を知っておくと、さらに覚えやすいでせう。「ゐ」は行為〔かうゐ〕の「為」、「ゑ」は恵比寿〔ゑびす〕の「恵」です。
「を」は〝現代仮名遣い〟では助詞(関係を示す語)に限られますが、正かなづかひでは助詞以外の語にも広く使はれます。読み方は助詞と変はらず「オ」です。五十音図を見て「を」がオ段にあるのを確かめて下さい。
以下、一例を示します。
語中語尾(語の始め以外の部分)のハ行(は・ひ・ふ・へ・ほ)は、ワア行(ワ・イ・ウ・エ・オ)で読みます。
ハ行の四段活用(は・ひ・ふ・へ)も同様です〔動詞などで規則的に変化する部分を「活用」と言ひます〕。ただし未然形(まだ実現してゐない状態を示す活用)に「う」が続く場合は「ワ」ではなく「オ」と読みます。
なほ例外的に「あふひ(葵)・あふぐ(仰ぐ)・あふる(煽る)・たふす(倒す)」などの「ふ」は、「ウ」ではなく「オ」と読みます。
語中語尾に「う」または「ふ」を含む見慣れない語があったら、その前の文字とセットで長音を含む語として読めないか試して下さい。概ね三つのパターンがあります。
「ア段+う」は、ア段をオ段にして長音で読みます。例へば「さう」なら「さ」が「そ」になり「ソー」と読みます。なほ正かなづかひでは未然形にオ段ではなくア段が使はれますが、同じ法則で読めます。
「イ段+う」または「イ段+ふ」は、「イ段+ュー」で読みます。
「エ段+う」または「エ段+ふ」は、エ段をイ段にして「ョー」を続けます。例へば「けふ」なら「け」が「き」になり「キョー」と読みます。
正かなづかひでは口語文においても、捨て仮名(促音や拗音にあたる文字を「っ・ゃ・ゅ・ょ」のやうに小さく書くこと)が用ゐられないことが多々あります。その場合は「つ・や・ゆ・よ」を小書きに直して読んで下さい。
ひとくちに正かなづかひといっても、和語のかなづかひと、漢語のかなづかひがあります。漢語のかなづかひは、漢字一字ごとの音に基づくかなづかひで、「字音仮名遣」と言ひます。漢字を直接読めればあまり気にする必要はないでせうが、ここでは字音仮名遣によく登場する読み方を説明します。
まづ、「くゎ・ぐゎ」は「カ・ガ」と読みます。
また「③ 語中語尾に「う・ふ」があるときの読み方」と関連しますが、「いう」「いふ」は「ユー」と読み、「えう」「えふ」「やう」は「ヨー」と読みます。
平安から明治まで長らく使はれてきた書き方を文語といひます。百人一首や「いろは歌」のほか、古典と聞いて想像されるであらう文体です〔とはいへ口語が主流の今でも「〜すべき」「〜のみ」など部分的に使はれてゐます〕。文語もここまでに紹介した読み方で概ね(意味はともかく音声としては)読めるはずですが、ここでは文語に特有の読み方を紹介します。
助詞の「む」は「ン」と読みます。「らむ・けむ・なむ」は「ラン・ケン・ナン」となります。
当文書はなにぶん国語の素人が書いたもので不足や妙なところが有り得ます。この解説ではよく分からなかったとか、ちゃんと専門家の解説を読みたいといふ方は、ぜひ参考文献を御覧下さい。